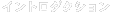

白磁のように素朴で温かい人がいた。日本が韓国を併合していた時代にあって、朝鮮の人々と友情を育み、荒れ果てた山を緑に戻す使命感に燃えたその人の名は、浅川巧。『道〜白磁の人〜』は、1931年に40歳の若さでこの世を去った浅川巧の半生を、史実をもとに描いた映画だ。
物語は日本の韓国併合から4年後の1914年から始まる。朝鮮林業試験所に勤めるため京城へとやってきた巧は、同僚の李青林(イ・チョンリム)とともに、荒れ果てた山に木々を取り戻すために努力を重ねていく。そして映画は、朝鮮の工芸品の価値を広めるための巧の活動や、巧と家族の絆、さらに独立運動が高まる中で巧とチョンリムに訪れる運命を描いていく。
浅川巧を演じるのは、ドラマ「平清盛」「南極大陸」や映画『孤高のメス』で活躍する吉沢悠。チョンリムには「朱蒙」で主演をつとめたペ・スビン。年齢も近い日韓の俳優ふたりが、立場を超えてふたりの間に築かれる絆を見事に表現してみせた。
そのほか、民藝運動で知られる柳宗悦に塩谷瞬、巧の妻・みつえに黒川智花、巧の人生後期に大きく関わる咲に酒井若菜と実力派若手俳優陣が共演するのに加え、市川亀治郎、堀部圭亮、田中要次、大杉漣、手塚理美が存在感を放ち、脇を固めている。
監督は高橋伴明。これまでも『光の雨』『丘を越えて』『禅 ZEN』『BOX 袴田事件 命とは』などで実在の人物・事件を題材としてきた高橋監督は、浅川巧の生き方をつうじ、日本と韓国の関係を改めて問いかける。
『道〜白磁の人〜』は、キャストだけでなく、スタッフも日韓の共同体制によって制作された。かつて浅川巧と李青林のように、日韓のスタッフ・キャストが結んだ絆の証、それが『道〜白磁の人〜』という映画なのだ。
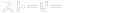

日本による韓国併合から4年を経た大正3年(1914年)。朝鮮半島の京城(現在のソウル)にひとりの若者がやってきた。山梨の農林学校で学んだ浅川巧(吉沢悠)である。
以前から京城で生活している母・けい(手塚理美)と兄の伯教(のりたか:石垣佑磨)は、やってきた巧を歓迎する。巧は、陶磁器を収集している伯教から朝鮮の白磁を見せられ、初めて見るその美しさに惹かれるのであった。
勤務先である朝鮮林業試験所へ初めて赴く朝、巧は路面電車の中で横柄な態度をとる日本の軍人の姿を目にした。軍人に強引に席を奪われた老人のために巧は自らの席を譲る。老人が口にする言葉の意味がわからない巧に、その言葉が「ありがとう」という意味だと教えてくれたのは、電車に乗りあわせていた朝鮮の若者だった。
その若者は、偶然にも巧と同じ林業試験所で働く李青林(ぺ・スビン)であった。荒廃した朝鮮の山々を緑に戻したいと考える巧は、チョンリムから朝鮮語を習い、養苗のための種子を採取するためチョンリムとともに山々を歩く。次第に友情を深めていく巧とチョンリムだったが、同時に巧は日本人の朝鮮の人々への振る舞いや日本人の差別的な感情を知り、複雑な想いにとらわれる。また、上司の町田(田中要次)たち、巧の態度を快く思わない人々もいた。
仕事に奮闘する一方、美術評論家の柳宗悦(塩谷瞬)と知り合い、生活に根ざした朝鮮の陶磁器の価値を伝えていくことにも決意を新たにする。さらに、山梨時代の友人・朝田政歳(市川亀治郎)の妹・みつえ(黒川智花)と結婚、1年後には娘の園絵に恵まれ充実した生活を送っていた巧だったが、朝鮮人の間には民族独立を目指す動きが活発化していた。そして――。



